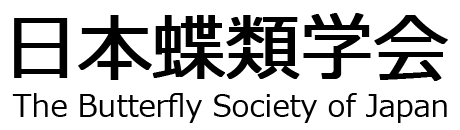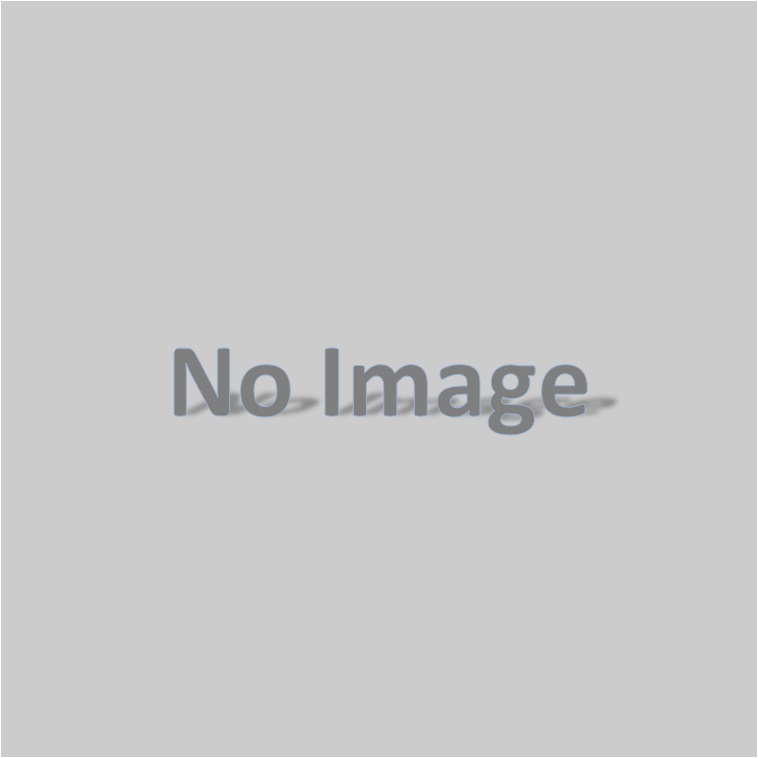会員の皆様こんにちは、この度日本蝶類学会会長に選任されました菱川法之です。
ここにお集まりの皆様は蝶が大好きで蝶を極めることに夢中の方々ばかりで、しかも各業界トップクラスの方々がひしめき合っている中で、何故小生が会長に選ばれたのか、無名のダークホースが三冠を取ったような有り得ない結末に足元が震える思いです。思い返せば世界の蝶の生態解明に心血を注いだ故五十嵐邁先生、日本産蝶類研究の第一人者・藤岡知夫先生、大屋厚夫先生、故宇野正紘先生、高橋真弓先生をはじめ、多くの蝶界の偉大な先達から教えを請い実践した結果今の私があります。偉大な先達の若き日のお顔が目に浮かびます。「いつかこの人のよう私になりたい、必ず超えてやる」と思いながら、未だに足元にも及んでいない私です。私も蝶・命の大好き人間で、特にモンゴルやヒマラヤの道なき道で珍蝶に出会うと脳内アミンと血中アドレナリンが一気に放出されるような快感をおぼえます。戦後日本人で初めてモンゴルのアポロウ スバシロチョウ Parnassius apollo を手にした時の興奮 (1992年の「月刊むし」に矢崎康幸氏がシリーズで連載)。バヤンウルギーから馬で登るモンゴルアルタイ山脈 (alt. 3,000 m) のコリアスモンゴラ Colias tamerlana monngola との出会い。インド北端のタガラン峠 (alt. 5,500 m) のアッコウスバ・マハラジャウスバ・カルトニウスウスバ P. charltonius。ヒマラヤ山脈南端ロータン峠のハードヴィッキーウスバ P. hardwickei、中国青海省アムネマチン山のプルゼワルスキーウスバ P. acco przewalskii、中国タクラマカン砂漠の最奥タシクルガンのヘリブトモンキ Colias wiscottii、キルギスタン内天山のダヴィドフウスバ P. davidovi、中国-ミャンマー国境徳拇拉峠稜線のノセウスバ P. nosei 等々。会員の皆様とたぶん全く同じで、人のやっていないことを一番乗りでする事が大好きなわがまま坊主で、 他人の思惑など上の空で今まで生きてきました。迷惑をお掛けした方々に今ここで深謝したい気持ちで一杯です。
さて、時の流れは容赦無く移りゆきます。少子高齢化の時代の波はこの会場にも押し寄せています。これから毎年のように会員の減少は避けられないでしょう。しかも若手は複数の学会に加入して多額の会費を支払っている状況です。日本蝶類学会、日本鱗翅学会、日本蛾類学会、日本蝶類科学学会など。これからも我々は、もっともっと楽しく生き残って行かねばなりません 。 この事実を肝に銘じて、これからどうすれば良いか皆さんで知恵を絞っていきましょう。蝶・蛾大好き人間の中高年世代と若手世代の明るい未来の為に。それでは若手の世代のみならず時代を担ってきた世代会員の皆様の益々のご活躍を祈念して日本蝶類学会新会長就任の挨拶とさせて頂きます。
2019年12月
菱川 法之
Hishikawa Noriyuki
菱川法之 (ひしかわ・のりゆき)
1947年東京生まれ。1971年北海道大学理学部卒業。1975年東京大谷専修学院卒業。1982年札幌医科大学卒業。1990 年医学博士。本土復帰前の沖縄・西表島横断からヨーロッパ、シベリア、モンゴル、ヒマラヤ、北朝鮮などを広く踏査し、主に蝶類の撮影を続ける。当会の理事を長く務め2020年からは会長。2018年には磐瀬賞を受賞。代表著作に「東アジ ア蝶紀行」(2003) があるほか、本書に収録された多くの写真は当会会誌 Butterflies に掲載されている。札幌市在住。
| 【会長】 | 菱川法之 |
| 【副会長】 | 増井暁夫(運営担当) 矢後勝也(学術担当) |
| 【理事】 | 坂田潤一(北海道:運営委員兼務) 工藤忠(東北) 伊藤勇人(関東:運営委員長兼務) 稲岡茂(関東:編集委員兼務) 上田俊介(関東:HP委員兼務) 上原二郎(関東) 小沢英之(関東:財務委員長兼務) 久保田瑛子(関東:HP委員長・編集委員兼務) 関康夫(関東) 長谷川大(関東:編集・HP委員兼務) 栗山定(関東:編集委員長兼務) 齊藤光太郎(関東:学術委員長兼務) 杉原由一(中部・東海:財務副委員長兼務) 渡辺康之(関西) 高崎浩幸(中国:編集委員兼務) 斎藤基樹(関東:運営委員兼務) Yu Feng HSU(海外) |
| 【監事】 | 辻元 井上健 |
| 【学術委員会】 | 学術委員長 齊藤光太郎(理事兼務) |
| 【運営委員会】 | 伊藤勇人(委員長:理事兼務)原田一志(IT・WEB担当) 粟野雄大 天野信之介 世良裕朝 楠本優作 斎藤基樹 志田智義 北浦広海 勝山礼一郎 深道直人 |
| 【編集委員会】 | 栗山定(委員長:理事兼務) 宇野彰(副委員長) 高崎浩幸(理事兼務) 稲岡茂(理事兼務) 長谷川大(理事兼務) 永幡嘉之 鈴木知之 久保田瑛子(理事兼務) 永井聖大 楠本優作(運営委員兼務) |
| 【財務委員会】 | 小沢英之(委員長) 杉原由一(財務副委員長) |
| 【HP委員会】 | 久保田瑛子(委員長)上田俊介(理事兼務)井上健 長谷川大(理事兼務) |
日本蝶類学会沿革
1992年(平成4年)
・日本蝶類学会発足。第1期会長は五十嵐邁氏。副会長は藤岡知夫氏
・Butterflies創刊号を発刊
1995年(平成7年)
・福田晴夫氏が第2期会長に就任
1998年(平成10年)
・福田晴夫氏が第3期会長に就任
1999年(平成11年)
・五十嵐前会長が名誉会長に就任
2001年(平成13年)
・日高敏隆氏が第4期会長に就任
2003年(平成15年)
・日高会長が任期途中で会長を辞任。加藤義臣副会長が会長代行に就任
・運営委員長(当時)により、「海外の博物館で行われた藤岡知夫氏の標本借受の手法等
には問題がある」との発議があり、理事会で協議がなされた結果、藤岡氏の除名が決定。
この処置に一部の理事、会員が反発し、学会の運営が困難になる
2004年(平成16年)
・学会運営の正常化を図るために、加藤会長代行が休会を宣言。学会誌発行等の組織活動
全般が休止状態になる
2005年(平成17年)
・「Butterflies自主刊行会」名義で本誌39号が発行され、活動が事実上再開される(現
在の本会の系譜)
・同名の別組織が「Butterflies 39号」を発行し、蝶類学会が分裂状態となる。2つの「蝶
類学会」及び「Butterflies」という組織と学会誌が併存する状況が2007年まで継続
・矢田脩氏が第5期会長に就任
2007年(平成19年)
・東京地方裁判所で両組織の和解が成立。それぞれの組織名称を「日本蝶類学会(テング
アゲハ)」及び「日本蝶類学会(フジミドリ)」とし、学会誌名もそれに準じることで合
意
2008年(平成20年)
・矢田脩氏が第6期会長に就任
・五十嵐名誉会長逝去
2010年(平成22年)
・「日本蝶類学会(テングアゲハ)」と「日本蝶類学会(フジミドリ)」の統合協議が、
目的を達しない状態で終了
2011年(平成23年)
・植村好延氏が第7期会長に就任
2014年(平成26年)
・横地隆氏が第8期会長に就任
2015年(平成27年)
・第1回夏のフォーラムを京都府で開催
2016年(平成28年)
・第2回夏のフォーラムを北海道で開催
2017年(平成29年)
・加藤義臣氏が第9期会長に就任
・静岡昆虫同好会との共催により、第3回夏のフォーラムを静岡市の「ふじのくに地球環
境史ミュージアム」で開催
2018年(平成30年)
・東京大学総合博物館との共催により、子供を主対象にした「昆虫採集・標本作製入門」
を東京大学で開催
2020年(令和2年)
・菱川法之氏が第10期会長に就任
・コロナ禍の影響により大会・総会の開催を中止
2022年(令和4年)
・初のオンライン大会を実施
・3年ぶりとなる対面による大会・総会を、オンラインとのハイブリッド形式で実施
2023年(令和5年)
・対馬博物館の自然史特別展「対馬の昆虫 陸橋の島の生物多様性」に併せて、同博物館と
の共催により、第4回夏のフォーラムを対馬市で開催
歴代会長
日本蝶類学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この学会は、「日本蝶類学会」(以下「本学会」という)と称し、英文ではThe Butterfly Society of Japan(略称「BSJ」)という。
(目的)
第2条 本学会は、広く蝶類及び蝶類に関連する事項の研究を推進し、知識を普及・向上させるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)学会誌「Butterflies」、連絡誌「Butterflies Newsletter」の発行。
(2)会員総会・大会・フォーラムの開催。
(3)蝶類の研究及び知識に功績のあった個人または団体の表彰。
(4)その他、本学会の目的を達成するに必要な活動。
第2章 会員
(会員)
第4条 本学会の会員(以下、「会員」という)は、本学会の趣旨に賛成するとともに本会則を承認し、かつ運営委員会が審査のうえ認める個人(「個人会員」)及び団体(「団体会員」)から構成される。
2.会員は、所定の年会費を納めなければならない。また、海外在住者は日本円に替えて相当額のUS$を会費に充当することができる。
3.会員は、本学会誌の配布を受けるとともに、本会則に定めるところに従い、本学会の運営と活動に参加する。
4.会員の入退会は、会計年度単位とする。
(資格の喪失)
第5条 会員は、次の理由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。(申告退会)
(2)個人会員が死亡し、または団体が解散したとき。
(3)会費を2年間滞納したとき。(認定退会)
(4)会の体面を著しく損ねる行為を行い、会員にふさわしくないと理事会が決議したとき。(除名)
第3章 役員及び委員
(役員)
第6条 本学会に、次の役員を置く。会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名。
(委員会)
第7条 本学会に、本学会の活動の実行機関として、運営委員会、財務委員会、編集委員会、学術委員会及びホームページ委員会を置く。
(会長及び副会長の選任及び職務)
第8条 会長は、全会員の直接選挙によって選出されるものとする。
2.会長の選挙においては、全会員が被選挙権を持つ。ただし、会員5名以上の連署による推薦のあった会員を会長選挙における会長候補者とし、同候補者の中から会長を選出する。
3.会長選挙の実施方法は、運営委員会がこれを定め、会員に告示する。ただし、会長の選挙は、会長の任期が満了する会員総会までに完了していなければならない。
4.会長は、本学会を代表するとともに、本学会の運営と活動を総括し、執行する。
5.副会長2名は、会長が会員から指名し、会員総会の承認を経て会長が委嘱する。副会長2名は、運営担当、学術担当とに分かれ、それぞれの分掌事項を通じて会長を補佐する。会長に事故のある場合、または会長が欠けた場合は、運営担当副会長が、さらにそれが欠けた場合は、学術担当副会長が会長の職務を代行する。
(名誉会員)
第9条 本学会の発展もしくは蝶学の発展に大きく貢献した者を本学会の名誉会員とすることができる。
2.名誉会員は役員を構成しない。
3.名誉会員は、会長が委嘱し、会員総会において会員に報告する。
4.名誉会員は、会費の納入を要しない。
(理事の選任及び理事会の職務)
第10条 理事候補者は、会員10名以上の連署により、会員の中から推薦される。
2.同一の会員が2名以上の理事候補者を推薦することはできない。
3.会長は、推薦された理事候補者のほかに、その裁量により、本学会の運営に有効と考える会員を追加して理事候補者とすることができる。ただし、この場合の理事候補者は15名を超えないものとする。
4.理事候補者は、会員総会の承認を経て会長が理事に委嘱する。
5.会長・副会長・理事は、理事会を構成する。
6.理事会は、会則改正案の審議を行う。
7.理事会は、会務執行状況、事業計画、前年度決算、来年度予算を審議・決議する。
8.理事会は、事務局所在地の変更、「日本蝶類学会基金」の使用の他、会長が必要と認めた事項について審議し、決議する。
(監事の選任及び職務)
第11条 監事は、本学会の会計を監査し、所要の事項を会長に報告しなければならない。
2.監事は、会員総会の承認を経て会員の中から会長が委嘱する。ただし、監事は、他の役員をかねることはできない。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。また、会長が要請した場合には、理事会に出席しなければならない。
(役員の任期)
第12条 役員は、会員総会での承認または報告をもって就任し、その任期は3年とする。ただし、会長・副会長の重任は、それぞれ二期までとする。
2.補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残存任期とする。
3.役員は、辞任または任期の満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(運営、財務、編集、学術及びホームページ委員の選任及び各委員会の職務)
第13条 運営、財務、編集、学術及びホームページの各委員会の委員は、会長が委嘱し、会員総会又は書面等(電子媒体を含む)において会員に報告する。
2.会長は、各委員会の構成員の中から、各委員会を統括する委員長を指名する。ただし、各委員長が理事を兼務することを妨げない。
3.委員会には副委員長を1又は2名置くことができる。副委員長は、理事会の承認を得て、委員長が委嘱する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4.運営委員会は、第3条に定められた活動内容に従い、他委員会と連携して本学会の活動方針等を企画検討し、その結果を事業計画として会長に提出する。また、会長により承認された事業計画を運営・実行する。
5.運営委員会は、第8条第1項に定められた会長の選挙を実施・管理する。
6.運営委員会での検討内容、合意事項や提案については、その都度記録を残すとともに、連絡誌「Butterflies Newsletter」等で随時会員に報告する。
7.財務委員会は、学会の収入・支出を管理し、当年度決算、翌年度予算案を理事会に提出する。また、「日本蝶類学会基金」を管理し、その収支状況を理事会に提出する。
8.編集委員会は、会誌「Butterflies」を編集・制作する。
9.学術委員会は、編集委員会の求めに応じ、「Butterflies」掲載予定論文の審査を行う。また、会長の諮問により「日本蝶類学会三賞」の候補者を指名し、受賞者を決定する。
10.ホームページ委員会は、他委員会と連携して、ホームページの企画立案、更新、管理及び運営を行い、本学会の情報を発信する。
(役員等の報酬)
第14条 役員及び委員は、報酬を受けない。
第4章 会議
(会員総会の種類とその召集)
第15条 本学会の会員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、会長が召集する。
2.定時総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会員の5分の2以上から会議の目的を記載した書面による請求があるとき、及び会長が認めたときに開催する。
3.会員総会の召集は、会議の目的である事項、日時及び場所を記載してあらかじめ会員に通知しなければならない。
4.対面による開催が困難と認められ、且つ理事の過半数の同意があった場合において、書面又は電磁的方法により会員総会を開催することができる。
(会員総会の決議及び報告事項)
第16条 会員総会は、出席会員(会員総会が書面又は電磁的方法により開催された場合は、書面又は電磁的方法による意思表示を行った会員)の過半数の賛成により次の事項を決議する。
(1)本会則の改正。
(2)本会則に定めた役員委嘱の承認。
(3)本学会の解散の決議及び残余財産の寄付先の決定。
(4)その他、会長が必要と認める事項。
2.会長は、次の事項を会員総会又は書面等(電子媒体を含む)において会員に報告する。
(1)会務執行状況。
(2)事業計画。
(3)前年度決算及び当年度予算
(4)本会則に定めた役員及び委員の委嘱。
(5)「日本蝶類学会基金」収支。
(6)その他会長が必要と認める事項。
(会員総会の議長)
第17条 会員総会の議長は、その総会に出席している会員の中から会長(または会長就任予定者)が指名する。
(理事会の召集及び決議)
第18条 理事会は、会長が召集するかまたは理事の5分の2以上から書面による請求があるとき召集され、会長がその議長となる。
2.理事会の決議は、委任状を提出した理事を含め、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の同意がなければならない。
3.緊急の決議を要する議題は、会長の判断により、通信による理事会を開催することができる。会長は、意見集約結果と決議事項を理事会構成員に知らせ、理事から要求があれば、その証拠となる資料を提出しなければならない。また、決議事項は直近のニュースレター等を通じ、会員に告知される。
(運営委員会の召集)
第19条 運営委員会は、会長の了承の下で、運営委員長または企画・財務担当副会長が召集し、召集者が議長となる。
2.副会長2名及び運営委員長のいずれかが必要と認めた場合は、運営委員に加え、各委員会委員を招集し、拡大運営委員会を開催することができる。
(議事録)
第20条 議長は、会員総会または理事会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、ニュースレター等で会員に報告する。
(1)開会の日時及び場所
(2)出席者数またはその氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む)。
(3)決議事項。
(4)決議の経過。
第5章 事務局及び支部
(事務局)
第21条 本学会はその活動にふさわしい場所を理事会が決定し、そこに事務局を置く。
2.事務局には、運営委員会の指揮の下にその職務を補佐する事務局員をおくことができる。
3.事務局の所在地は、理事会の議決により、変更することができる。
4.事務局の所在地は以下の通りとする。
〒113-0001 東京都文京区白山1-13-7 アクア白山ビル5階 勝美印刷㈱
(支部)
第22条 本学会は、理事会の承認を経て、内部組織として支部を設置することができる。
2.支部が設置された場合には、当該支部に責任者1名を置く。
3. 支部の運営と活動については、運営委員会がこれを定める。
第6章 財務
(会計等)
第23条 本学会の一般会計は、会員が納入する会費、寄付金等によって支弁するものとする。
2.本学会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
3.本学会は、会費の徴収、予・決算、事業報告及び事業計画の作成を会計年度ごとに行うものとする。
4.一般会計とは別個に、「日本蝶類学会基金」を設置する。その金額は、会長により会員総会又は書面等(電子媒体を含む)で会員へ報告される。
5.「日本蝶類学会基金」は、会長の権限において適正に運用する。
6.「日本蝶類学会基金」は、過去3年間の運用益の残高について、会長の権限において本学会の事業に使用することができる。
7.「日本蝶類学会基金」の過去3年間の運用益の残高を越える支出は、理事会の決議を必要する。
第7章 会則の改正及び解散
(改正)
第24条 本会則の改正は、会長または理事会の発議により、会員総会で決定される。
(解散)
第25条 本学会の解散に伴う本学会の残余財産の処分は、会員総会の議決を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
2.本学会が解散したときは、会員総会の指名する清算人が清算を実行し、清算終了後その結果を会員に報告する。
第8章 付則
第26条 本会則に必要な事項は、本会則で別に定めるものを除き、運営委員会の討議と合意を経て別に定める。
第27条 削除。
第28条 第19条第2項で規定した拡大運営委員会で立案され、会長が認めた場合は、翌年度会費を変更することができる。
第29条 第1条で規定した名称について、当学会と名称の類似する他学会の区別が困難な場合には下記の通称名を用いることとする。
通称名:「日本蝶類学会(テングアゲハ)」
The Butterfly Society of Japan (Teinopalpus)
会誌名:「バタフライズ(テングアゲハ)」
Butterflies (Teinopalpus)
(制定:1991年10月10日)
(最終改正:2024年12月14日)